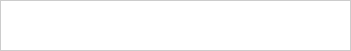≪自己評価表≫
保護者向け・自己評価表 ⇒ こちら
事業所における・自己評価表 ⇒ こちら
≪事業所における自己評価結果≫ (別紙3)
| ○事業所名 | 特定非営利活動法人あるく・自律を目指す会 放課後等デイサービス・児童発達支援 つきのおあしす | ||||
| ○保護者評価実施期間 | 2025年1月6日 | ~ | 2025年 1月 20日 | ||
| ○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 23 | (回答者数) | 13 | |
| ○従業者評価実施期間 | 2024年12月23日 | ~ | 2025年1月10日 | ||
| ○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 9 | (回答者数) | 8 | |
| ○事業者向け自己評価表作成日 | 2025年1月30日 | ||||
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
| 1 | 重度知的障害児が多いため支援の有り方も工夫が求められる。その中で地域活動や戸外活動も定着してきている。このことは、講師や市施設関係との信頼や繋がりが増してきていることがあげられる。具体的には、ヨガ活動およびスポーツ等の心身への効果がみられる活動であり、図書館へ定期的に行くことなどである。今後は、農園作業に定期的に通うことも予定している。 | 支援プログラムの公表は、現在ホームページに載せているが、5領域の支援を理解していただくために、職員会での理解とプログラムを実践に重ね合わせる作業が重要となる。そのため、実践していく内容と実践してきた内容を子供たちに同様にルーティン化した形で居場所を再構成するかという課題は、大変時間を要する。特に、重度知的障害や行動障害の多い当事業所において時間がかかりかつ形骸化しやすい。職員会・研修・打ち合わせを効率的に生かして意識的に取り組んで行く予定である。 | 現在、支援記録、保護者向け連絡帳、即日℡連絡(子供の出欠・健康状態・家庭事情)・職員会および内部研修や日誌は、すべて紙と手書きで行ってきている。非常勤職員含めたすべての職員がかかわる上で、必要な方法として持続してきている。しかし、一方で保護者の立場においては、デジタル化することで日々の連絡が安易で簡単で見やすい時代に入っていることも事実である。今後検討していきたい。 | ||
| 2 | ヒヤリハット報告が多く出され、危険に対する意識が増していること。虐待防止の話し合いが現場に生かされていること。居場所の安全と安心を保護者が理解されている段階にある。今後は、PDCAサイクルに則りヒヤリハット後の対策から事後検証と、再度チェックし改善した状態を職員が十分に共有して支援の向上を目指す事である。 | 業務改善のためのPDCA化について、職員会の内容の経過がPDCAになっている場合も多くあるが、意識的にPDCA化していくための取り組みとなると、話し合いの資料提供の内容を理解しやすいよう工夫を図る必要がある。そのことによって、職員自体がPDCAが必要であることを感知し主体的な関わり化可能と思う。そのように工夫しながら、職員に働きかけていきたい。字あkンがかかると思われる。 | 当事業所の利用児童は、年少児も多く市全域に住居が広がっている。現在2台から3台の送迎車を運転できる職員と添乗者を配置し送迎を行っている。一般的に年少児を中心として送迎時間は1時間が限度とされる。そのための、乗車人数の検討や送迎車の台数、障害度合いに合わせた運転者と添乗者の総人数の確保は今後充実を図るための取り組みのひとつである。 | ||
| 3 | コミュニティノート(本人の意識に立った過ごし方のアセスメントづくり)を作成しモニタリング作業も行い、当事者の視点を観察できるちからを養いつつあること。このことにより、本人の気づきを常勤職員を中心として養う力に結びついている。今後は、個別支援計画との連動性を強め、具体的支援により結びついたプログラムへの展開ができるよう努めていきたい。 | デイサービスのガイドラインおよび5領域に関連した本人支援、家族支援、移行支援等の理解と実践は、職員会がパイプとなっている。文言の内容と日々の具体的実践の距離を縮められるよう、資料をいくつかの観点から深められるよう提供している。法人の理念や方針をより理解してもらうことが近道であり、そこから具体的支援プログラムを実践に生かせるよう意識していただくよう、また話し合う機会を増やす工夫をしている。 | 打ち合わせ(毎日)を常勤同士午前中行い、非常勤(パート)職員の出勤を15分早め、意識的に、前日の振り返りその日の役割分担や子供の情報等を行っている。これらの効果は職員の現場の意識の変化に繋がっている。今までの打ち合わせを拡充し、職員が意識して職務に入り仕事に納得感を得られるための方策としている。 | ||
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
| 1 | 保護者会およびペアレントトレーニング等のご家族への参加できる研修会や個人指導が可能な力量を組織として職員の質として高められることが課題であると考える。個別面談等を通して子供の変化や様子の共有は行っているが、保護者が家庭内で参考になる育児方法など、積極的に提案できるレベルに達していない。 | 現在ペアレントトレーニングは、支援者にとっても有効な支援の研修内容であるため、ここを糸口にして相互に共感できる場づくりを提案していくことが肝要と感じる。加えて、本人支援の状況を伝えていくことで、御家族へ積極的に関わりを持つ力となり、実践の基本と思われる。 | 保護者会開催やご家族支援においては、事業所の健康イベント等と併せて予定化することで、場を共感できる体制に開催して繋がりを創造していく工夫をしていく。個別面談では不可能な内容で、必要とされる組織上保護者に伝達すべき緊急時の規約や防犯・感染上のマニュアル等も伝達していく。 | ||
| 2 | 一般児童との交流や保護者同士の交流の機会の提供は、開設当初より低くなってきている。市民や保護者においても求める方が減ってきている現状であるが、放課後等デイサービス等が一般化してきた現象でもある。そのため、私たちが持続してきた活動(ヨガ活動など強味の活動)に合わせ、予定化する。 | 建物自体の構造や便宜性について必ずしも交流しやすい場所ではない。現在児童が通う特別支援学校の近隣に事業所配置している。しかしながら、通学している特別支援学校に近く学校との連携上より便利でもあり自然も近くにある。建物や地理的な不便性に変え、地域のセンター等の資源を利用することで利用家族をはじめ地域の多くの人的資源と交流できるチャンスを力としていく所存である。 | 基本的には利用児童の地域資源利用化に向け交流を促進していく。当事業所の活動として次年度は、当市活動支援センターを年間仮予約している。保護者会や市民あるいは学童保育を利用している児童とも交流を検討したい。今まで学童保育と交流するスペースは困難であったため、学童保育事業所と隣接した市民センターも含めて予定化の工夫をしていく。 | ||
| 3 | 組織的に必要とされる様々な規約・規則は職員が理解することで組織の円滑な運営と職員(非常勤)の質の向上になる。開かれた場所においてあるが、ともすると法律用語や専門様式により、職員にとって結びつきが薄くなっている。ひとつの具体的活動の背景にあるこれらの規約等々を職員が理解していく場を増やしていきたい。 | 組織に必要で職員の理解が不可欠な規約等を人的資源に浸透させるかについて、就業規則と運営規定、BCPとリスクマネージメント、業務マニュアルとガイドラインと大きく3分割していく。そこから、様々な細則を確認していく作業をする中で望んでゆく。大枠を捉えることで現実との接点が保てるよう実践ができるよう仕組みづくりをしていく。 | 職員が主体的に働く条件づくりを更に追及することは、当小規模法人にとっても不可欠であるため、東京都の働き方改革に沿いつつ、就業条件の整備を継続する。それと両輪になる利用者支援における安全管理の徹底業務がある。特に、非常時対応マニュアル等は普段忘れがちになるため定期的に確認作業を行っていくことが求められ、この二つを満たしていくことが主体的な働く場づくりとなる。 | ||